高取焼
Takatori Ware
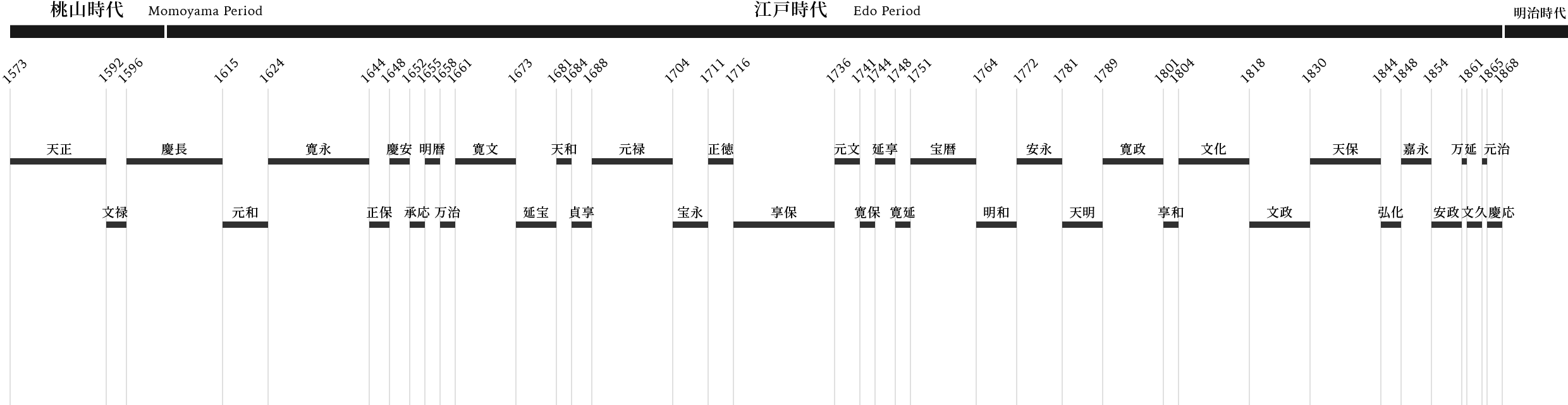
ホーム > 美術品一覧 > 日本古美術(商品のご案内ページへ)
高取焼
高取焼とは筑前国福岡藩・黒田家の庇護を受け、御用窯として焼成された陶器です。
幾度もの移窯を経ながら、藩窯の伝統を継承しつつ、
小堀遠州の美意識に応える茶陶を中心に焼成したことで、
「遠州七窯」の一つとして名声を確立しました。
その起源は文禄・慶長の役に際して、渡来した陶工・八山(和名:高取八蔵)が、
初代藩主・黒田長政の命により鷹取山麓(現:福岡県直方市)に開窯したことに始まります。
開窯年代は諸説あるものの、長政が関ヶ原の軍功により、
1600(慶長5)年に豊前国中津から筑前国福岡へ移封され、
初代藩主となった後の1602(慶長7)年頃に永満寺宅間窯での活動が開始されたと推定されています。
1614(慶長19)年には内ヶ磯窯へ移り、
古田織部の豪快な意匠(沓形、変形、掛分釉など)を積極的に取り入れ、当時の茶陶の潮流に俊敏に応じました。
織部亡き後は将軍家の茶道具指南役を務めた小堀遠州の「綺麗寂び」の理念が浸透していきます。
1623(元和9)年の長政逝去を機に、1624(寛永元)年に八山父子は朝鮮への帰国を願い出ますが、
2代藩主・黒田忠之の勘気に触れ、嘉摩郡上山田村(現:福岡県嘉麻市)に蟄居を命じられました。
ここで山田窯を開き、少数の門弟とともに日用の器を焼成しました。
忠之は茶器蒐集に強い情熱を持つ人物であり、
八山の蟄居に伴い、多くの陶工が釜ノ口窯(上野焼)へ移動しました。
1630(寛永7)年、忠之の許しを得て八山父子は帰参し、
白旗山麓(現:福岡県飯塚市)に白旗山窯を開窯しました。
これに先立ち、忠之の命により伏見で遠州の指導を受けたと伝えられ、
瀟洒で洗練された薄造りの茶陶「遠州高取」が多く焼成されました。
内ヶ磯窯でもすでに遠州好みの茶入が焼成されていたことが陶片から確認されていますが、
白旗山窯を境に作風は大きく変化し、特に茶入に優品が多く見られます。
高取焼の名を歴史的に高めたのは、まさにこの「遠州高取」の華麗にして瀟洒な造形美にほかなりません。
遠州所持の国焼茶道具の中でも、高取焼は重要な位置を占めています。
1654(承応3)年、八山はこの地で生涯を閉じました。
その後も3代藩主・黒田光之、4代藩主・黒田綱政の時代に移窯や増窯が繰り返され、
1665(寛文5)年には小石原鼓窯(現:福岡県朝倉郡東峰村)へ移窯しました。
天和年間(1681-84)には福岡城内で細工を行い、
上覧の後に小石原鼓窯で焼成したという記録も残されています。
1688(元禄元)年には大鋸谷窯(現:福岡市中央区輝国)へ移窯しますが、
長崎奉行からの不相応な依頼品を焼成したことで光之の勘気を受け、1704(元禄17)年に閉窯となり、
以後約12年間、高取藩窯の活動は休止しました。
宝永年間(1704-11)には荒戸新町(現:福岡市中央区荒戸)に御陶山が設けられ、
1716(享保元)年には東皿山窯(現:福岡市早良区祖原)が開窯されました。
これが藩窯の流れを汲む最後の窯となり、1871(明治4)年の廃藩置県まで活動が続けました。
現在では高取八山、高取八仙、鬼丸碧山、亀井味楽らを中心に、
伝統技法による「遠州高取」の風格が受け継がれています。
綺麗寂びの美学を宿す器は静かな華やぎと深い品格を湛え、茶の湯の世界において尊ばれています。
永満寺宅間窯 1602(慶長7)年頃~1614(慶長19)年
永満寺宅間窯(現:福岡県直方市永満寺)は高取焼発祥の地とされる最初期の窯です。
筑前国(黒田藩)と豊前国(細川藩)との国境に位置し、
釜ノ口窯(上野焼)が隣接しています。
直方市教育委員会は1982(昭和57)年に発掘調査を行いました。
焼成室6室と焚口1室から成る全長16.6mと小振りな地上式割竹形登窯で、
出土陶片から碗、皿、壺、瓶、甕、擂鉢等が確認されており、
僅かに茶陶も含まれています。
海鼠の体表を見るような青白く呈色した釉薬に特徴があり、
作品数は非常に少なく珍重されています。
永満寺宅間窯跡は1988(昭和63)年に直方市指定無形文化財に認定されています。
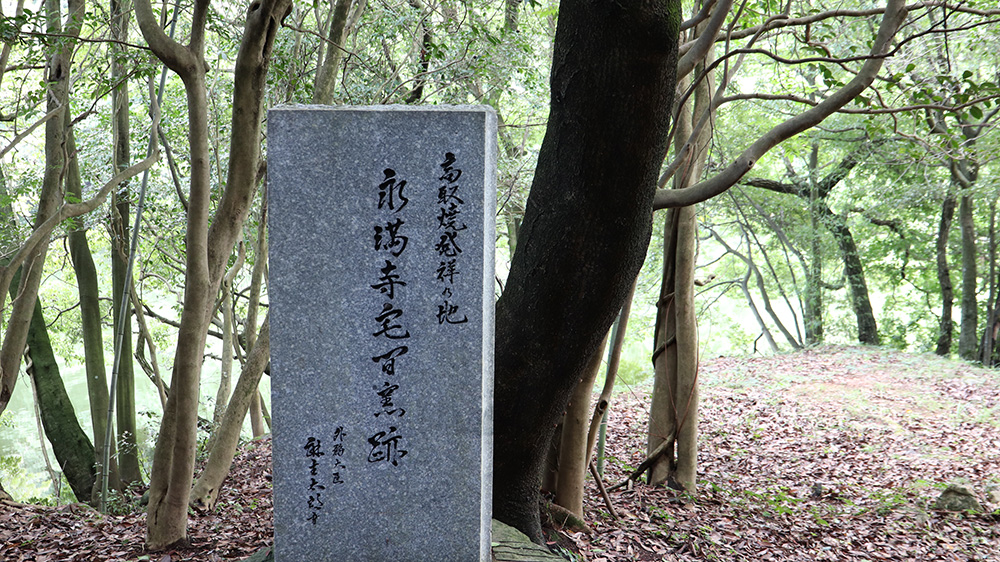

内ヶ磯窯 1614(慶長19)年-1624(寛永元)年
内ヶ磯窯(現:福岡県直方市)は永満寺宅間窯を凌ぐ焼成能力を備えた窯であり、
土灰釉、藁灰釉、飴釉、長石釉、銅釉、掛分釉等の多彩な釉薬に加え、
叩き成形を始めとする高度で多様な技法を駆使し、個性豊かで大胆な織部好みの茶陶を展開しました。
福智山麓に福智山ダムの建設が計画された事に伴い、
直方市教育委員会は1979(昭和54)年から1981(昭和56)年にかけて発掘調査を実施しました。
全長46.5m、焼成室14室と焚口1室から成る大規模な連房式登窯が確認され、
茶入、茶碗、水指、花入、向付等の茶陶に加え、日常使いの器物も多数出土しました。
この調査報告に基づき、従来は唐津焼、上野焼、萩焼に分類されていた多くの優品が、
内ヶ磯窯の作と再認識され、陶籍が変更されました。
『筑前国続風土記』には高取八山達の他、五十嵐次左衛門一派の存在も記されており、
彼は肥前国唐津藩主・寺沢志摩守広高の家臣であり、瀬戸焼の陶法に通じていた人物です。
2代藩主・黒田忠之は神屋宗湛を介して、五十嵐を召し抱え、八山達と共に、
自らの好みに適う品々を焼成させたと伝えられています。









