上野焼
Agano Ware
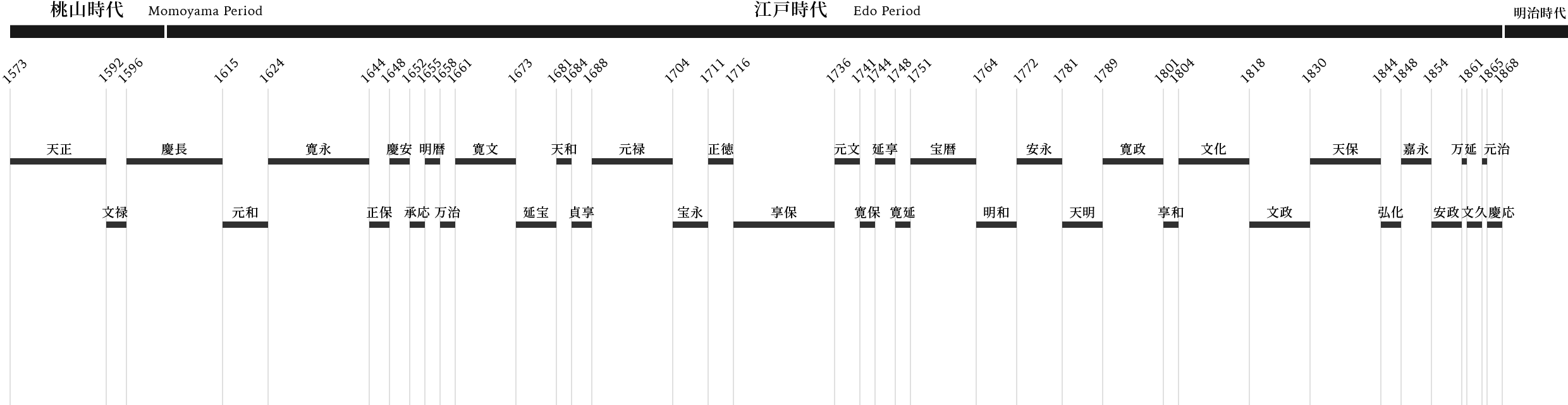
https://tenpyodo.com/product1/cat/japan/(取扱商品一覧 ⇒ 日本古美術)
上野焼
上野焼とは豊前国小倉藩細川家の庇護の下に御用焼として焼成された陶器です。
小堀遠州の好みを受けて創出された「遠州七窯」としても知られています。
初代藩主・細川忠興(号:三斎)は関ヶ原の軍功で丹後国宮津から豊前国中津に国替えとなり、
1602(慶長7)年に豊前国中津から豊前国小倉へ入封しました。
忠興は渡来陶工・尊楷(和名:上野喜蔵)を召し抱え、
上野郷に本格的で大規模な形態を備えた「釜ノ口窯」を開窯しました。
釜ノ口窯は優れた茶陶を数多く創出し、本流としての活動を成した事で著名です。
釜ノ口窯だけでは供給が不十分であった為、「岩屋高麗窯」も続いて開窯されました。
岩屋高麗窯は釜ノ口窯の厳しい均整美とは相反した民需用の自由奔放な要素が伺えます。
又、上野郷諸窯とは別に小倉城下には藩主自らのお好み窯(菜園場窯)も知られています。
その後、1632(寛永9)年に2代藩主・細川忠利が肥後国に移封した事で、
上野焼は播磨国明石より入封した小笠原家に引き継がれました。
忠興が八代城に入封すると忠興に務める尊楷も二子の忠兵衛と藤四郎(徳兵衛)を連れ、
肥後国で「八代(高田)焼」を焼成しました。
一方、三男・十時孫左衛門と娘婿・渡久左衛門は上野郷に残され、
小笠原家の庇護の下に「皿山本窯」を中心として二家共同で製陶に携わりました。
享保年間(1716~1736)には吉田家も加わり、
1871(明治4)年の廃藩置県まで藩窯として活動しました。
釜ノ口窯 1602(慶長7)年頃~1632(寛永9)年
釜ノ口窯(現:福岡県田川郡福智町上野)は優れた茶陶を数多く創出し、
本流としての活動を成した最初期の窯です。
日本陶磁協会は1955(昭和30)年に発掘調査を行いました。
焼成室15室と焚口1室から成る全長41mと大規模な連房式登窯で、
土灰釉、藁灰釉、飴釉等を用いて多くの日用品も焼成されました。
茶碗や向付等には高台内まで釉薬が施された総釉の作例が知られており、
高台の畳付部分には貝、砂、籾殻等の痕跡も確認されています。
尚、茶入や上手の作品は匣鉢に入れて焼成されたとも伝えられています。
筑前国(福岡藩黒田家)と豊前国(小倉藩細川家)との国境に位置し、
技法や造形に高取焼と共通性が見られる事からも技術の交流があったと推定されています。
其々において時代の好みの変化に応えるように数々の名品が焼成されました。
隣接する内ヶ磯窯(高取焼)が閉窯すると多数の陶工達は釜ノ口窯に流入しました。
1632(寛永9)年、2代藩主・細川忠利の肥後移封に伴って閉窯しました。
菜園場窯 江戸初期(正確な操業時期は不明)
菜園場窯(現:福岡県北九州市小倉北区菜園場)は、
初代藩主・細川忠興(号:三斎)のお楽しみ窯(趣味で茶陶を焼成した窯)と伝えられます。
1982(昭和57)年の北九州都市計画道路鋳物師町線改良工事の試掘調査中に窯跡が発見され、
上野諸窯の中では釜ノ口窯と並んで最初期に属し、
操業期間は窯構造の規模と出土遺物量より5年から8年位と推測されています。
焼成室4室と焚口1室から成る全長16.6mと小振りな地上式割竹形登窯で、
茶入、茶碗、水指、向付等を主体とした茶陶が焼成されました。
薄い鉄釉を掛けた焼締調の陶片資料が多い事も本窯の特徴です。
1987(昭和62)年、福岡県有形文化財(考古資料)に指定されました。
岩屋高麗窯 1607(慶長12)年頃~1632(寛永9)年
岩屋高麗窯(現:福岡県田川郡福智町弁城)は釜ノ口窯だけでは供給が不十分であった為、
釜ノ口窯から約5年を経ての開窯と推測されています。
釜ノ口窯の厳しい均整美とは反し、民需用の自由奔放な要素が伺えます。
日用品を中心とし、僅かに茶陶も焼成されました。
隣接する内ヶ磯窯(高取焼)が閉窯すると一部の陶工達は岩屋高麗窯に流入しました。
1632(寛永9)年、2代藩主・細川忠利の肥後移封に伴って閉窯しました。
皿山本窯 1624(寛永元)年頃~1871(明治4)年
皿山本窯(現:福岡県田川郡赤池町)は、
1624(寛永元)年から1625(寛永2)年頃にかけての開窯と推察されており、
約250年間という長期間に亘り活動しました。
釜ノ口窯と並立していた為、初期の作品には類似する作風のものが確認されています。
1632(寛永9)年に2代藩主・細川忠利が肥後移封後、
播磨国明石より小笠原忠真が入封しました。
尊楷の三男・十時孫左衛門と娘婿・渡久左衛門は上野郷に残され、
小笠原家の庇護の下に皿山本窯を中心として二家共同で製陶に携わり、
享保年間(1716~1736)には吉田家も加わります。
藁灰釉、灰釉、鉄釉、三彩、イッチン掛け、象嵌、刷毛目、紫蘇手等、
装飾や技巧性に富む多彩な技法が駆使され、
中でも酸化銅を使用した緑青釉は皿山本窯の代名詞とも云えます。
1871(明治4)年の廃藩置県をもって藩窯としての使命を終えました。





